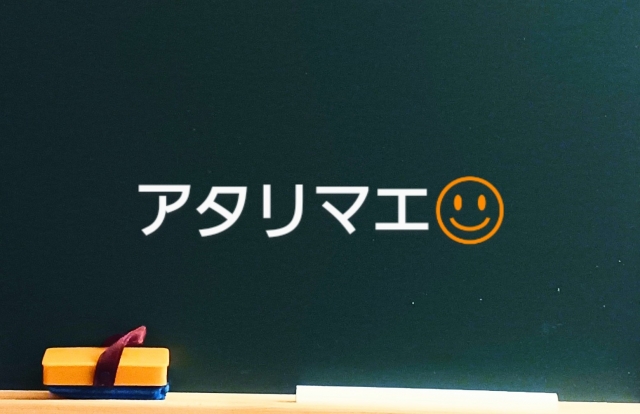
税理士業で欠かせないものに会計システムがあります。
数多くあるサービスの中から一社をメインとして選びました。
選定基準はいたって単純で、当たり前の対応してくれたからです。
幾つかの会社に問い合わせたり、声をかけてくれたところもあったのですが、
送ると言って資料をくれなかったり、
それきり連絡が来なかったり、
ノーアポで訪問されて、こちらが対応できなかったり、
なかなかなご対応もありました。
そういった中で、当たり前の対応していると感じたところを選びました。
他山の石といいますが
翻って自分も、約束を守る、問い合わせには確実に返信するといった
当たり前の対応を心がけております。
税理士に対する不満でよくある「連絡がつかない」「連絡・対応が遅い」といったことがないよう
以下の点を心掛けています。
- 問い合わせにはなるべく当日中に回答し、遅れる場合はひと言連絡します
- ご希望を十分にお伺いし、出来ること、できないことは明確にお伝えします
- ご不明点がないかは都度お伺いして、疑問が残らないように努めています
- 期日があるもの、長期にわたるものはざっくりでもスケジュール感をお伝えします
- 預かった資料は必ず返却します
自分でも遅くなるのが嫌なのと、早めに対応したほうが安心なので、
こういった事態にならないようにしています。
当たり前とは
しかし、「当たり前」がだんだん通じなくなっているのかもしれません。
上記の通り、対応不足に対する不満は尽きません。
また、こちらは当たり前と思っていても、
最近は価値観の多様化というのでしょうか、
常識が伝わらないこともあるのかとたまに思います。
会計や税務の分野では「一般に公正妥当と認められる範囲」や「社会通念上妥当」
という判断基準があります。
これらの基準は、ある程度共通した社会規範、
「当たり前」の感覚が社会に存在していることを前提としています。
具体的な金額や水準は時代によっても変わりますので、
どう判断するかは様々な議論、検討がなされながら、理解できる範囲内で運用されてきました。
4 第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
法人税法第22条第4項
使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。
(1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。
所得税基本通達 36-21
最近、ネット上ではこの曖昧さを盾に、
「因習だ」「基準が明確でない」「法律に明文化されていない」
だから「自分で決めてOK」といった強気な主張を目にすることもあります。
前述の通り、長らく様々な議論されているところをすっ飛ばしているので
私としては単に「常識の欠如」を公然と表明していると感じますが、
こうした主張に賛同する方も一定数存在するようで、
従来の慣習に対する見方の変化を感じています。
だってネットで言っていた!では根拠がなく曖昧なのは変わらないんですけどね…
こういう人たちに「当たり前」を通しても、ただの老害になってしまうので、
過去の判例、議論の経緯などで理解をしていただく必要があると思います。
相手が手っ取り早い結論にたどり着いた分、こちらが説明の負担を抱えますね。
余談
ところで、今使用している会社も対応にムムム?と思うことはあります。
しかしシステムは使えていますし、
いらないサービスは断っているので上手に付き合えれば問題ないと思います。
100%理想のものは存在しないし、
自分が最適化したほうが早いですしね。
とはいえ、いらないサービスを断って以来めんどくさい奴だと思われたのか、
担当者がびくびくしている気がしますが…すいません。
でも繁忙期に挨拶回りとか誰も幸せにならないですよ。


